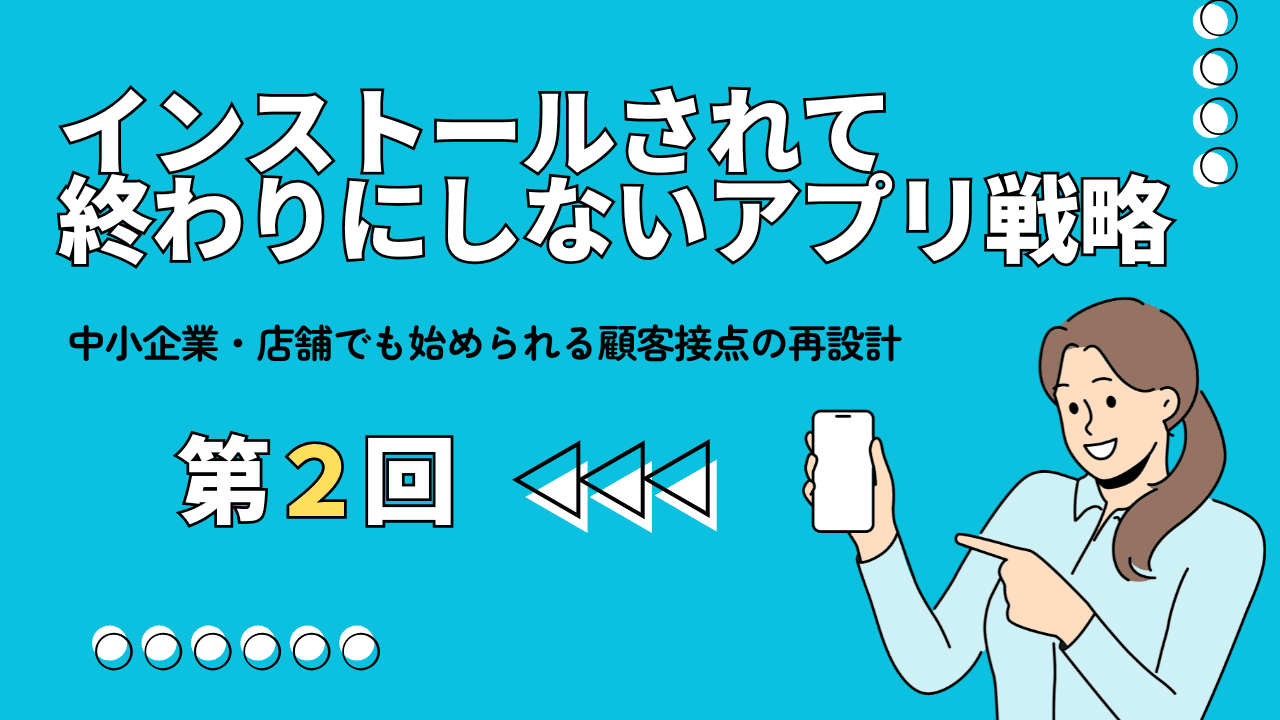
アプリを導入しても、「誰も使ってくれなかった」「結局インストールされただけで終わった」。
そんな苦い経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、アプリが「使われる」か「使われない」かを分けるのは、機能の多さやデザインの良し悪しではありません。
もっと根本的な、“ユーザーとの関係性”や“導入の目的”の違いが影響しているのです。
アプリが“使われない”主な理由
まず、多くのアプリが使われなくなる原因は、おおよそ次のようなものです。
導入時のメリットが弱い:インストールする理由が乏しい
使い続ける理由がない:更新頻度が低い、通知が一方的
生活動線に入り込んでいない:日常の行動や目的とアプリが結びついていない
単なる情報発信ツールになっている:アプリを開かなくてもLINEやHPで足りてしまう
一言でいえば、“アプリが生活の中で必要とされていない”のです。
ポイントカードのデジタル化だけでは、ユーザーの心には残りません。
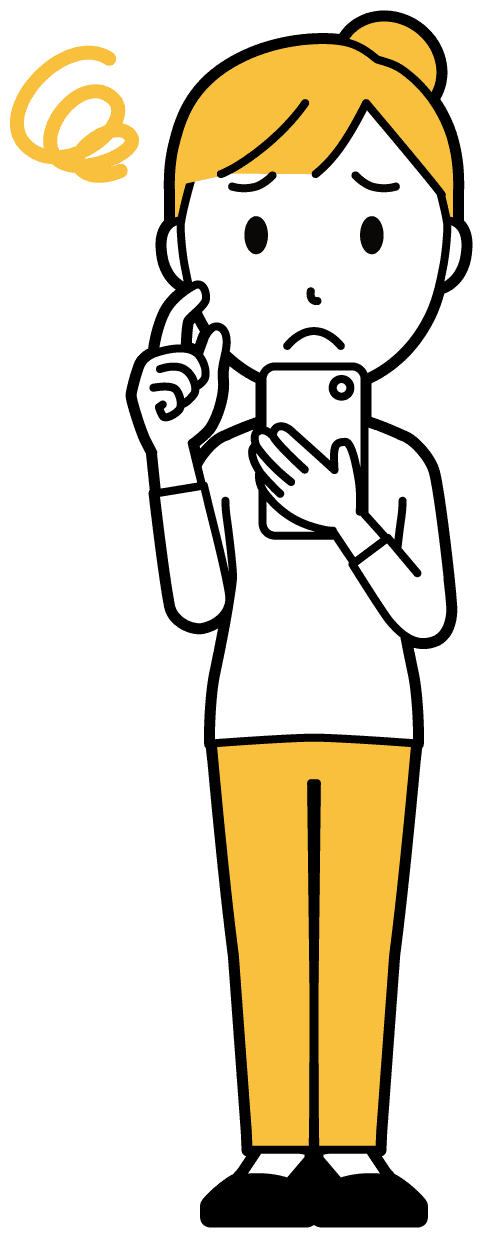
“選ばれるアプリ”は何が違うのか?
一方、使われているアプリには、必ず「ユーザーにとっての理由」が存在します。
お得・便利が“すぐそこ”にある
例)アプリ限定のクーポン、ポイント確認、会員証提示など操作がシンプルでストレスがない
例)2タップ以内で会員証表示、来店スタンプがすぐに押せるユーザーの行動を前提に設計されている
例)来店時に自然と使う動線、スタッフに促される利用シーン“使って得した”体験が記憶に残る
例)誕生日にアプリで割引が届いた、来店ポイントでギフトをもらった
これらはすべて、“ユーザー目線の設計”がなされている証です。
単なるツールではなく、「ちょっと便利で、ちょっと得する」存在として、アプリが生活の中に溶け込んでいるのです。
店舗や中小企業でも、“選ばれるアプリ”は作れる
「それって大手企業だけでしょ?」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
むしろ、中小規模の店舗や地域密着型のビジネスこそ、“顔が見える関係”と相性のよいアプリを活用すべきです。
スタッフがアプリ利用を声かけできる距離感
限られた顧客層に向けた“刺さる施策”が打てる柔軟性
地域のイベントや商圏に合わせた使い方ができる自由度
こうした現場の強みを生かせば、使われる理由のあるアプリ設計は、決して難しい話ではありません。
“導入する”から“定着させる”へ
アプリを入れることがゴールではなく、“どんな体験を提供し、どう使い続けてもらうか”こそが本質です。
そのためには、「誰に・どんな価値を届けたいのか?」という視点からの設計が不可欠です。

